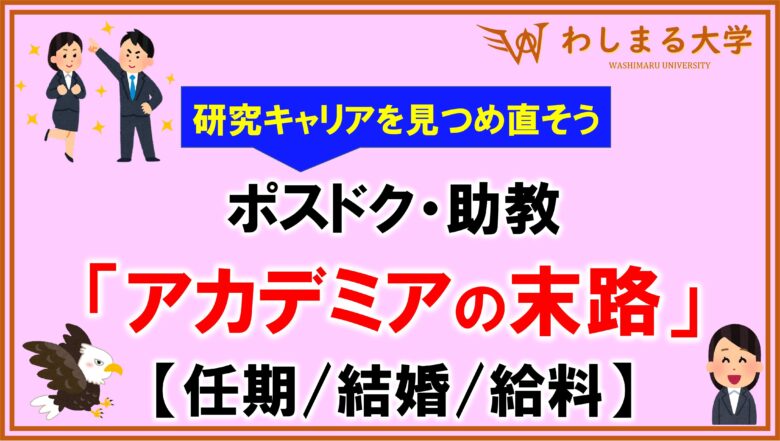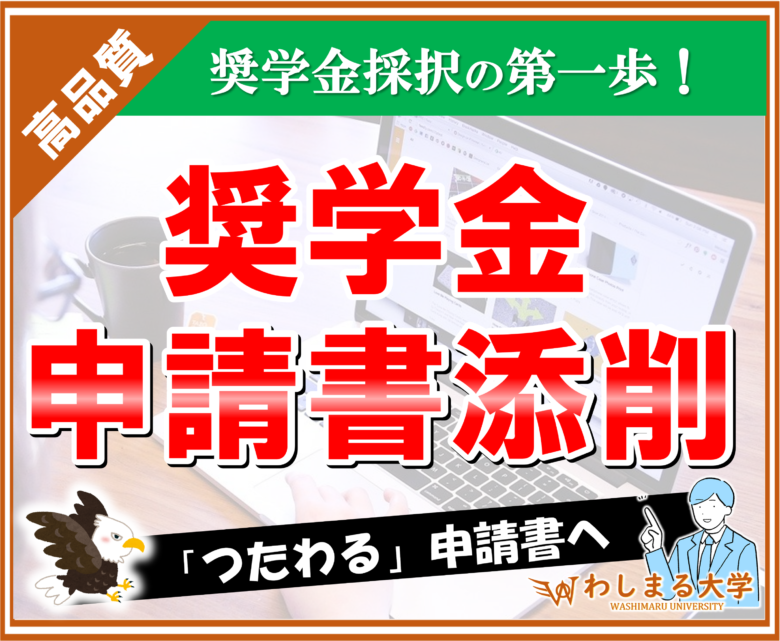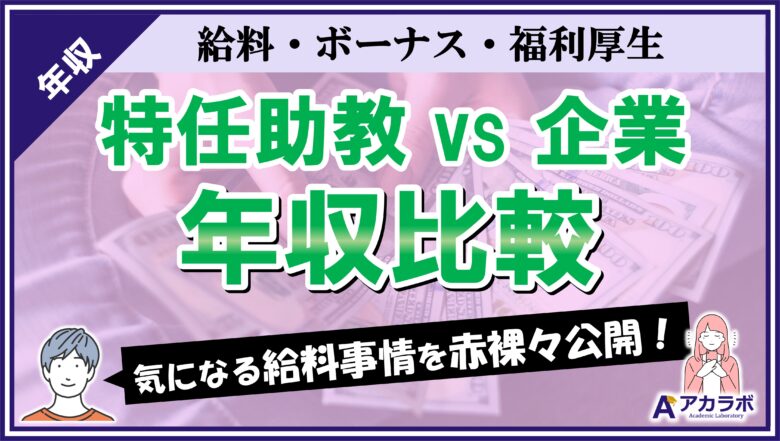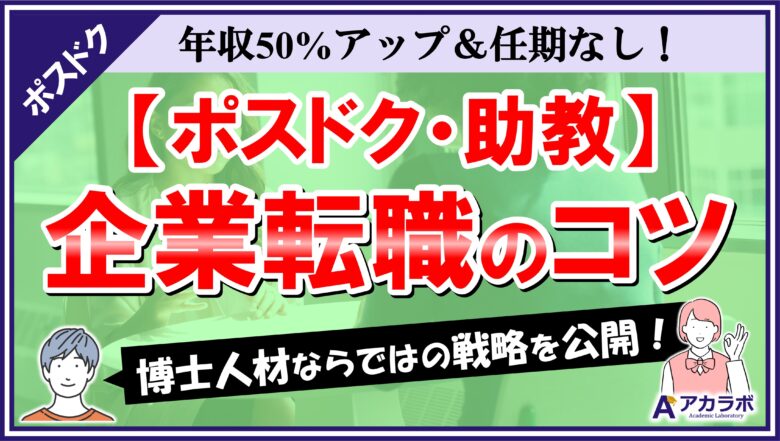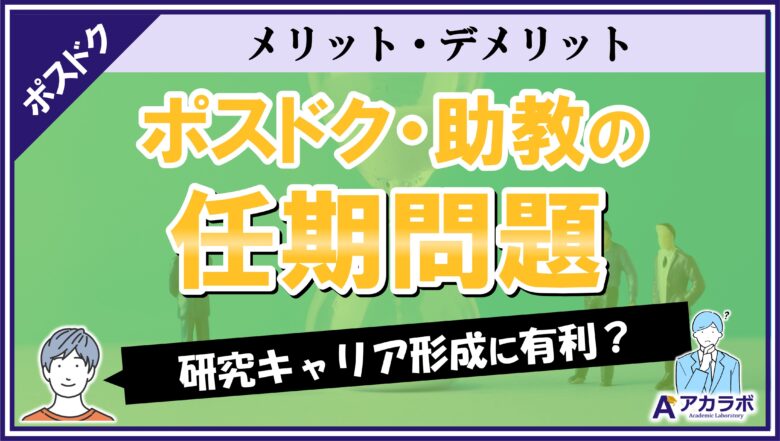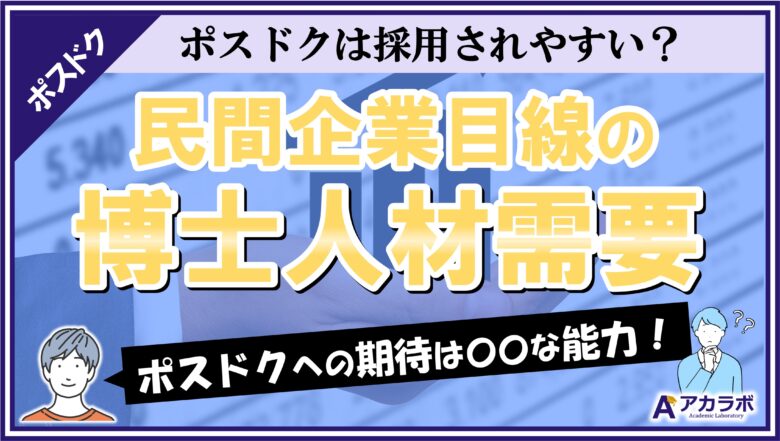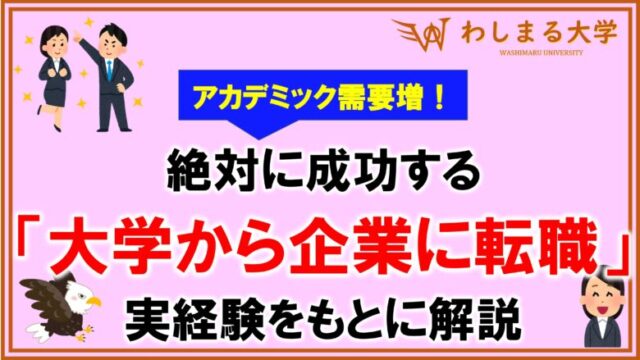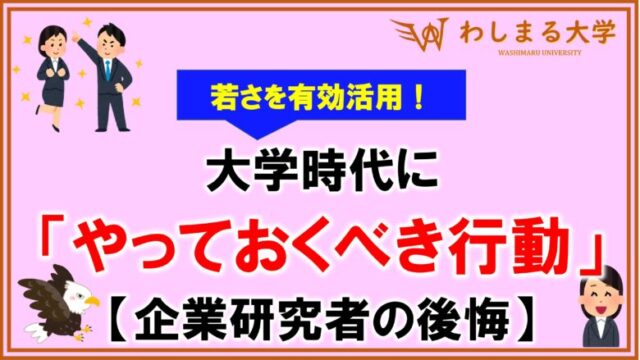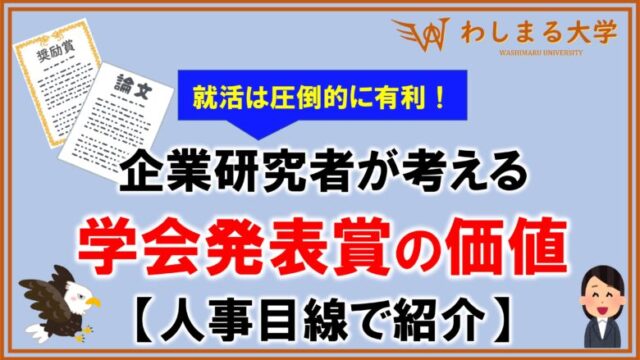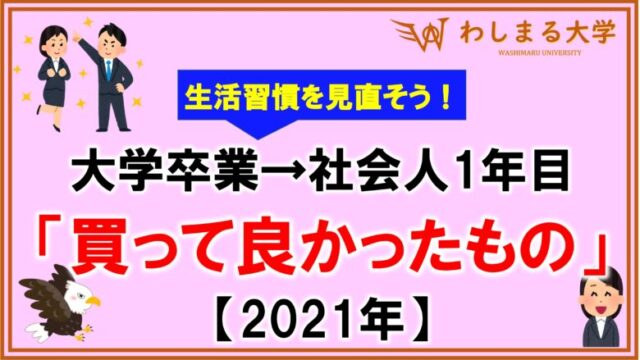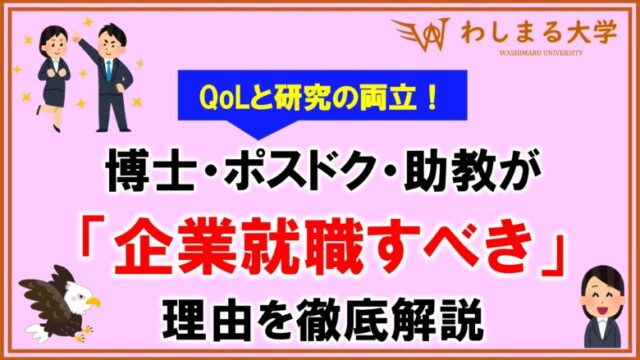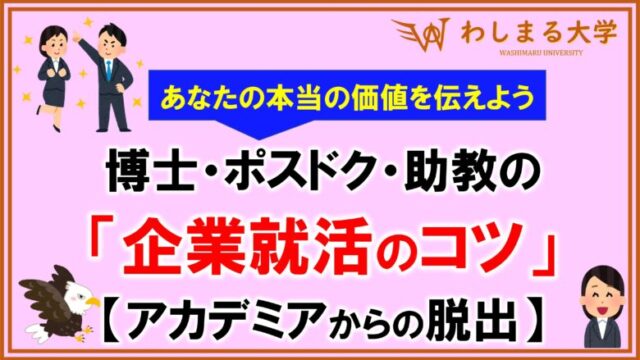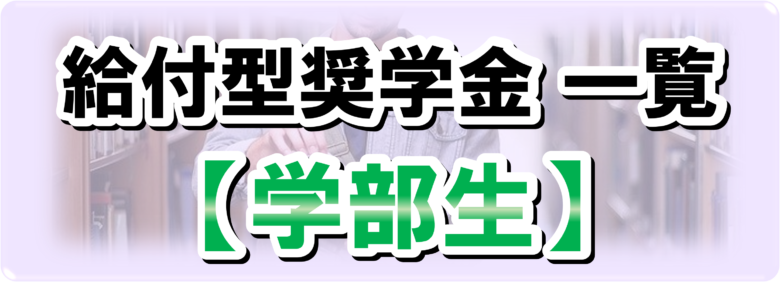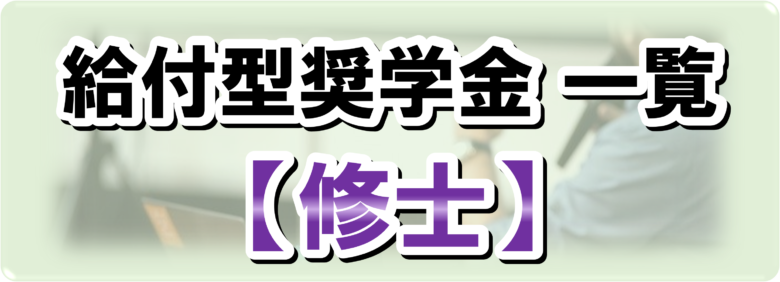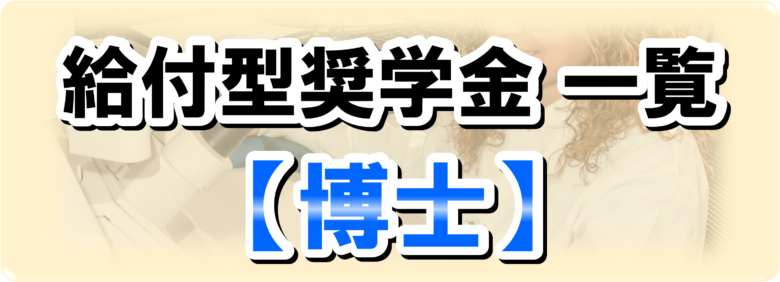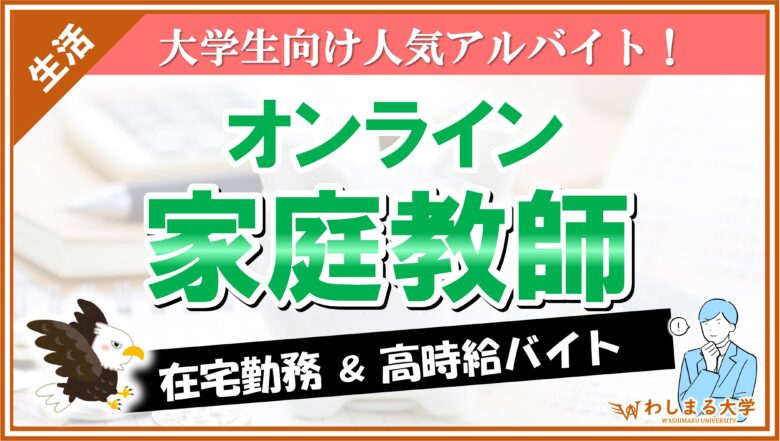現在、博士学生やポスドク、助教をしている人の中には、このままアカデミックの世界でうまくやっていけるのか不安に思っている人もいるのではないでしょうか?
本記事では、アカデミアから企業に移った先生方の経歴や企業転職を決めた理由、その後の企業内での活躍などを複数例紹介していきます。
【ポスドク/助教】アカデミックキャリアの末路

それでは、ここからアカデミアから企業にフィールドを移した方々の経歴を紹介していきます。
タイトルは「末路」という言葉を使い少々刺激的な表現になっていますが、どの先生も自分自身の性格や能力特性を真剣に見つめ、より良い人生のために一歩踏み出すことができた素晴らしい方々です。
決して、大学の先生方の雑談で意図される「脱落者」のようなニュアンスを持って紹介しているわけではないことを理解いただいた上でご覧いただけたらと思います。
【特任助教】大学時代の同期との給料差に不安→民間企業研究職に

アカデミアから企業へ転職した1例目は、ポスドクの給料の少なさに不安を感じて民間企業に転職した特任助教Cさんです。

特任助教 C さん
博士号取得 → 地方大学特任助教(2年間) → 企業研究員(29歳)
特印助教Cさんは、博士号取得後すぐに特任助教というポジションを獲得して大学で研究を続けていました。
しかし、大学院時代から定期的に参加していた同期との飲み会で、年々給料差が大きく広がっていることを不安に感じていました。
ポスドクの年収の低さはニュースなどでも取り上げられることが多くなってきましたよね
自分が持っている専門性の高さが自身の給料に反映されないことに苦しくなってきた特任助教Cさんは、海外ポスドクポジションや民間企業転職を目指して就職活動を開始します。
最終的に自身の専門性をそのまま活かす事ができる企業研究所を見つけて中途採用にエントリーした結果、無事内定を勝ち取ることができ今も楽しく研究活動を続けているようです。
【補足】ポスドクと民間企業の給料差
実際にポスドクから民間企業へ転職した人の年収比較が紹介されている記事を紹介します。
3年任期の特任助教から民間企業研究所へ転職した結果、
- 入社1年目:年収464万円(ポスドク比 1.4倍)
- 入社2年目:年収643万円(ポスドク比 1.8倍)
- 入社3年目:年収1,301万円(ポスドク比 3.6倍)
と、大幅な年収アップに成功しています。
入社3年目は海外駐在員として抜擢されたための大幅昇給となったようです。
このようなチャンスを得る可能性の高いアカデミア人材は、企業研究所での活躍も選択肢に入れても良いかもしれませんね。
実体験をもとにしたポスドクから企業転職する際のコツについては以下の記事でまとめられています。
【ポスドク】実験は好きだけど論文が書けず任期切れ→非正規研究員として民間就職

アカデミアから企業へ転職した2例目は、実験は好きだけどなかなか論文が出せず非正規の企業研究員に移られたポスドクAさんです。

ポスドク A さん
博士号取得 → 地方大学ポスドク研究員(7年間) → 任期切れ再雇用なし(論文0) → 中小企業の非正規研究員(35歳)
ポスドクAさんはある実験に長年取り組んでおられ、専門の研究内容や装置に関して非常に詳しい知見を持っている人でした。
本当に実験が好きで朝から晩まで毎日休まず働き続けていたのですが、問題はなかなか論文を書けないことだったのです。
教授もポスドクAさんのキャリアを気にすることはなく、最終的に任期切れで雇い止めになりました。
今は任期なしのポスドクや助教公募はほとんどありませんもんね
研究業績は多くはなかったものの、幸いなことに中小企業の非正規研究員として雇ってもらい、今でも好きな実験を続けているようです。
【補足】ポスドクの任期問題
年収の低さに加え、任期付きで不安定であることがポスドクポジションの問題であると指摘されることが多いです。
最近では、ポスドク研究員や助教だけではなく、准教授ポジションですら任期付きであることが一般的になりつつあります。
任期があるからこそやる気が継続するといったメリットもある一方で、研究者自身の人生が不安定になったり研究室移動コストがきついといったデメリットも多くあります。
- 【精神面】40代頃になるまで不安定な生活が続くため精神的につらい
- 【移動費】研究室を引っ越しするための費用負担が大きい
- 【研究規模】目先の成果獲得に走りがちになる
- 【家庭】結婚や出産子育てなどの将来的な家族計画を立てづらい
企業の専門職として研究者採用されれば任期なしで研究できますので、そのあたりもポスドクと企業の大きな違いだと言えますね。
【ポスドク】実験サポートが好きだと気づく→研究所の実験補助員に中途採用

アカデミアから企業へ転職した3例目は、実験サポートが好きだと気づき研究所の実験補助員に転職したポスドクBさんです。

ポスドク B さん
修士号取得 → 企業開発職(5年間) → 大学に戻り博士号取得(4年間) → 私立大学ポスドク研究員(2年間) → 企業の実験補助員(36歳)
ポスドクBさんは修士号取得に一度企業に就職したものの、自分には合わないと感じて博士号を取りに大学に戻られました。
学位取得後ポスドクとして大学に残りますが、アカデミアというよりも共同研究や指導学生の実験サポートが好きだったのだと気づき、転職を考え始めます。
ポスドクBさんは非常に優秀な方で、コミュニケーション能力や情報収集能力、教育力などで高いスキルを持っており、転職活動でも複数の内定をもらうことができました。
最終的に企業研究所の実験補助員に転職することを決め、今でも楽しく実験を続けているとのことです。
研究活動にも、実験や論文執筆、学会発表、教育など様々な要素があります。その中で自分が本当に好きなのは何なのかを考えてみるのも、より良いキャリア形成にとって重要かもしれませんね
【補足】博士人材は企業に求められている?需要はあるの?
今大学で研究者をされておられる方の中には、企業への転職も気になっているけれど「自分自身が企業に求められているのか?本当に採用してもらえるのか?」と不安に感じている人もいると思います。
しかし、結論から言えば博士人材は企業から求められており、大きな需要があると言えます。
- アカデミックスキルは企業でもそのまま通用するから
- 企業の中途採用が積極化しているから
- アカデミア経験人材は今後ますます需要が高まるから
- 企業側も大学でのキャリアアップの難しさに理解があるから
博士人材の持つ論理的思考力や情報収集能力、教育能力といった能力は、企業で研究を進める場合でも必須のスキルです。
また、最近のジョブ型雇用へのシフトの流れの中で、高度な専門性を持つ博士号持ちは年々有利な状況になりつつあります。
あなたの持つ専門性の高さがどの企業で求められているのか、一度求人情報(非公開求人含め)を確認してみるのも良いかもしれませんね。
【特任助教】大学時代から続く遠距離恋愛に限界を感じる→大企業転職&結婚

アカデミアから企業へ転職した4例目は、長年に及ぶ遠距離恋愛に終止符を打つため企業転職した特任助教Dさんです。

特任助教 D さん
博士号取得 → 旧帝大特任助教(1年間) → 企業研究員(28歳)
特任助教Dさんは、大学時代から付き合い始め4年間以上遠距離恋愛していた彼女から、
「遠距離をそろそろ解消したい」
「結婚も考えたい歳だけど任期付きのまま結婚は難しい」
と言われ続けていました。
任期のあるポスドクや助教だと奥さんも将来不安に感じてしまいますよね
Dさん自身も遠距離恋愛に疲れていたのですが、一度だけでもアカデミアポジションを経験しておきたいと言う気持ちから、特任助教になって大学で勤務します。
しかし、半年ほど予算獲得を経験したり周りの先生の人事模様を間近で見た結果、このままだと40歳を超えるまでテニュアポジションは取れないと改めて実感しました。
また、装置や物品、安全対策の管理のほか、学生の教育、学生実験、書類仕事などの雑用が非常に多いことも改めて大変だと気づきました。
しかも、それらの雑用は准教授や教授に昇進するほど多くなっていくのです。
准教授、教授になると、助教のときとは比較にならない量の雑務が降り掛かってきます。
引用:アカデミアより企業研究者を選ぶべき理由を徹底解説
授業、研究費取得・管理、学生指導、事務対応、学会運営、教授会等の大学運営、研究室管理者、業者対応、査読、
などなど、挙げだすとキリがありません。
これらのアカデミアの大変さを身をもって実感したDさんは、すぐに企業へ転職することを決意します。
これまでわがままを通した負い目もあり、彼女の勤務地近くの企業研究所を狙い転職活動した結果、幸いにも近い研究内容で企業研究所に採用されることが決まりました。
その後無事に結婚され、幸せな生活を過ごしているようです。
【助教】教授からの論文執筆圧力に耐えきれず→企業研究職に転職

アカデミアから企業へ転職した5例目は、教授からの論文執筆圧力に耐えきれず企業転職した助教Eさんです。

助教 E さん
博士号取得 → 国研ポスドク研究員(3年間) → 旧帝大助教(3年間) → 企業研究員(34歳)
助教Eさんは、国研ポスドクを経験した後、旧帝大の助教として採用されます。
年間1報のペースで論文を書いていたのですが、所属研究室の教授からはもっと量産する必要があると言われつづけていました。
ただ、研究テーマ的にも論文を量産できるような内容でなく、かと言って論文が出せそうな新規テーマを始めるための予算獲得や本人のモチベーション維持が難しいという状況が続きます。
研究費を取るためには、優れたアイデアだけではダメで、その実現性を担保するための実績も必要です。つまり、新テーマの分野で十分な実績(論文、特許、学会発表)がなければ研究費を獲得することはできないということです。
引用:アカデミアより企業研究者を選ぶべき理由を徹底解説
本人の現状と教授から求められる研究者像とのギャップに耐えきれず企業転職を決意することになりますが、これまで地道に積み重ねてきた実績が高く評価され、同分野の研究員として無事企業研究所に採用されました。
とても良い先生でしたので、無事に同分野の転職先が決まって安心しました
【助教】業績のない古株が内部昇進していくアカデミックの悲惨さに嫌気→企業研究職に転職

アカデミアから企業へ転職した6例目は、研究業績がない古株が内部昇進していく惨状に嫌気が差して企業転職した助教Fさんです。

助教 F さん
博士号取得 → 海外ポスドク研究員(10年間) → 地方大学助教(4年間) → 企業研究員(41歳)
助教Fさんは、海外ポスドク研究員を10年間経験しており、大変優秀な研究者でした。
大学内でも突出した成果をあげており、すぐにでも准教授に上げるべき人材だという声もありました。
しかし、ここで大学の悪い部分が出てしまいます。
ある時、Fさんと同じ学科の准教授枠が2つ空いたのですが、どちらの枠も大して業績を出していない古株助教が内部昇進してしまったのです。
都合のいいところだけ業績勝負にするのに、いざというときにはコネを重視するのはどうかと思いますね
その実態を間近で見たFさんは、アカデミアの理不尽さに嫌気が差し、すぐに企業転職してしまいました。
非常に優秀な研究者であったこともあり、転職後すぐに管理職として昇進し今でも企業研究員として活躍されておられます。
最近ではポスドク問題、アカデミックポジション不足問題が企業の中でも知れ渡ってきており、簡単に准教授や教授にはなれないことは常識になりつつあります。ポスドクや助教の中にも埋もれている優秀な人材がいると期待されており、積極的に採用される可能性が高いです。
引用:「企業転職は必ず成功する」と断言する理由をくわしく解説
【助教】大して業績もない教授が威張っているアカデミアに我慢できず→企業研究職に転職

アカデミアから企業へ転職した7例目は、大して業績がない教授や准教授までもが威張っているアカデミアに我慢できず企業転職した助教Gさんです。

助教 G さん
博士号取得 → 旧帝大ポスドク研究員(7年間) → 地方大学助教(5年間) → 企業研究員(39歳)
助教Gさんは、実験だけでなく学生の教育も好きでアカデミックの世界に残ります。
競争的資金も安定的に獲得し順調なキャリアを歩んでいたのですが、アカデミアに対する不満が積もっている部分もありました。
特にGさんは、任期付きポジションが導入され始めた年代にポスドクとしてアカデミアに入ったため、業績がなくてもテニュアを取れてしまった准教授や教授が大きな顔して残り続けている状況にあったのです。
全員テニュア時代と任期導入の狭間にいる40代前後の先生方は本当に苦労されておられます…
そんななか、あることをきっかけに研究室の教授と喧嘩し、これ以上耐えきれないと考えて企業転職を決意します。
近しい分野の研究員として採用され、入社後すぐに実力が認められ昇進。まだ40歳代前半ですが、すでに管理職として年収1300万円以上もらっているようです。
先が見えない変革の時代を生き抜くためには、常に最新の情報にアンテナをはり、新たなアイデアを生み出し続ける能力やバイタリティを持った人材が必要になります。この需要にピッタリの能力を持ち合わせているアカデミア人材は、今後さらに企業に採用されやすくなるだろうと推測されます。
引用:「企業転職は必ず成功する」と断言する理由をくわしく解説
【准教授】上司の任期延長で溜め込んでいた不満が爆発→企業研究職に転職&年収UP
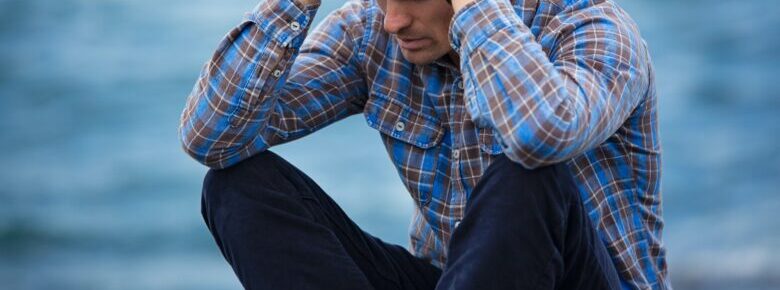
アカデミアから企業へ転職した8例目は、上司の任期延長でアカデミアに対する様々な不満が爆発し企業転職した准教授Hさんです。

准教授 H さん
博士号取得 → 地方大学助教(6年間) → 地方大学准教授 (4年間) → 企業研究員(37歳)
准教授Hさんは、名の知れた有名教授のもとで順調に准教授まで昇進します。
ハイインパクトな論文誌に多数掲載され、大型の研究費も当てるなど、順風満帆なアカデミア人生を歩んでいました。
このような順調なキャリアの一方で、「A教授についている研究者」という周りからの目は気になり続けていました。
特任助教Cさんも独自性で悩んでいましたよね
教授の退官が近く、その時を待ち続けるも、身近にいた教授が自らの政治力を利用して任期延長するのを目の前で何度も経験します。
そのような経験からアカデミアに対する嫌気と諦めの気持ちが大きくなっていき、最終的に企業転職を決意しました。
入社後の年収は准教授時代の1.3~1.5倍に上がりました。
さらに、Hさんの実力の高さは企業でもすぐに認められ、入社2年後にスピード出世で管理職になり、今でも研究者として活躍されておられるようです。
【まとめ】研究キャリアを見つめ直してみよう!
本記事では、アカデミアから企業に移った先生方の経歴や企業転職を決めた理由などを複数例紹介してきました。
本記事に対する感じ方は人それぞれだと思います。
・アカデミアを辞めた理由を見て「自分だったらこれくらいであれば問題ない」と感じる人
・アカデミアについて「これまで成功例しか見てこなかったんだ」と気づいた人
・30歳代半ばで転職されている実例が多かったのを見て「もっと早めに企業に移ったほうが得だ」と考えた人
それぞれの気づき、感じ方をもとにして、あなたが本当に歩みたい研究キャリアがどのようなものかを改めて考えるきっかけになれば幸いです。
大学には本当に優秀な研究者が多くいると感じています。定年退職するときに後悔しないキャリアを歩むために、今改めて自分の人生プランを考えてみてほしいと思います
これまでずっとアカデミアにいた人にとって新たな選択肢となる企業転職を少しでも考えている人は、転職成功のコツを押さえて新たな環境に向けた第一歩を踏み出してみてください。
以上で、アカデミアから企業に移った先生方の経歴紹介は終わりです。
ご不明点等有りましたら、お気軽にツイッター「@Washimaru_UNIV」までご質問ください。
お疲れ様でした!
\アカデミアからの脱出!/